火災予防に役立つ動画
通電火災にご注意を!感震ブレーカーを設置しましょう
通電火災とは、地震により発生する電気火災の一種で、地震直後ではなく、発生後しばらくして発生するといわれています。
これは、停電により途絶えていた電気供給が、復旧により再通電したことにより火災になるもので、原因としては、
・電気ストーブなどの発熱を伴う電気機器に、倒れてきた可燃物が接触した
・揺れにより倒れた重量物が、電気配線に損傷を加えた状態で電気が流れた
などが考えられます。
これら通電火災を防ぐために有効なのは、ブレーカーを落としてから避難することです。
しかし、そうはいっても「いざというときそんな余裕はない!」という方もいらっしゃると思います。また、外出先での被災も考えられます。そのような場合におすすめなのが「感震ブレーカー」です。
「感震ブレーカー」とは地震の揺れを感知して、自動的にブレーカーを落としてくれる装置です。「感震ブレーカー」について、詳しい内容をこちらの動画にまとめました。ぜひご覧ください。
【動画】感震ブレーカーについて
あああ
反射式石油ストーブからの火災に注意しましょう
反射式石油ストーブは電源を必要としないため、どこでも使用でき、とても重宝されます。しかし、直火や高温部が露出しているため、石油ファンヒーターなどと比べて、使い方を間違えると火災になりやすいといわれています。
そこで、実際に起きた火災を例に、反射式石油ストーブからの火災を防ぐポイントを動画で確認しましょう。
【動画1】ガソリン誤給油による火災
【動画2】洗濯物の落下による火災
【動画3】吹き返し現象と着衣着火
あああああ
コンロ火災に注意しましょう
毎年、全国の出火原因の上位を占めるのが「コンロ」です。「コンロ」による火災で最も多いのは、鍋等の放置によるものです。
最近のガスコンロには、ガス漏れや鍋の過熱を感知して自動で止まる「Siセンサー」がついていますが、それでもコンロ火災は後を絶ちません。
Siセンサーの機能では予防できないコンロ火災の姿を、温度を実測しながら分かりやすく動画でお伝えしますので、ぜひご家庭の『火の用心』に生かしてください。
【動画】コンロ火災の再現実験
あああ
たばこ火災に注意しましょう
全国の出火原因の第1位である「たばこ」。多くは火を消したと思い込んで捨てられた吸い殻が原因となって出火しています。
電子たばこが主流になっている一方で、直火を使用する従来の「紙巻きたばこ」の不適切な後始末は、かけがえのない命や住まいを奪います。
そこで、上越地域消防局では、たばこによる火災原因の一つとなり得る「ガラス灰皿からの出火」を再現する火災実験を行いました。たばこ火災を防ぐためのポイントを確認し、たばこ火災を予防しましょう。
【動画】吸い殻の不始末による火災
あああ
電気火災に注意しましょう
全国的に火災件数が減少している中、「電気」に起因する火災は増加傾向にあります。最近は、オール電化住宅やリチウムイオン電池を電源とする製品の増加など、これまで以上に電気との関わりが密接になってきており、その取扱いには正しい知識が求められます。
一般的に、ストーブやガスコンロといった機器に比べて、出火リスクを認識しにくい点が「電気」の怖いところです。
数ある電気火災の中でもよく見られる「タコ足配線」を例に、再現実験を交えた注意喚起動画を作成しました。ご家庭、事業所等における電気機器のご使用状況やコンセント周りの点検をお願いします。
【動画】電気火災を防ぐために
ああああ
引火性液体の危険物取扱いは細心の注意をお願いします
引火性液体の危険物は火がつきやすい(揮発しやすくガス化しやすい)ので注意が必要です。また、ガス化した危険物は爆発しやすくなるので、次の点に注意して貯蔵・取扱をお願いします。
・高温注意(夏季、火の近く、直射日光は要注意)
・貯蔵は冷暗所で(容器は密閉し、ガス化しにくい場所で保管)
・取扱いは風通しの良い場所で(ガス化してもすぐに薄まれば安全)
上越地域消防局ではガソリンの爆発実験を実施しました。引火性液体の恐ろしさをぜひご覧ください。
【動画】ガソリン爆発実験
【動画】ガソリン火災のメカニズム
あああああ
意外と熱い!?「燻炭焼き」の燃焼実験
稲刈りが終わると各地で多く行われる「燻炭(くんたん)焼き」。
正しい方法で行わないと、火災の原因になることがあります。上越地域消防局では農家の方のご協力のもと、燻炭焼きの燃焼実験を行い、その結果を動画にまとめました。ぜひご覧ください。
【動画】燻炭焼の実験
問合せ 上越地域消防局 予防課 ☎ 025-545-0230
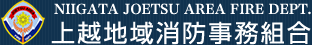
 翻訳
翻訳